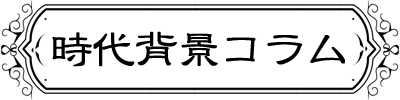
第2回 「飛行機」
明治44年(1911年)頃の若者たちにとって、「飛行機」とはどのような存在だったのでしょうか?
まずは飛行機の歴史を振り返ってみましょう。
いきなりですが、世界で最初に飛行機で空を飛んだ人は誰でしょう??
ライト兄弟を思い浮かべる人が多いかと思いますが、答えはドイツ人のリリエンタールです。
ライト兄弟は1903年12月17日、世界初の「動力付き飛行機に乗って飛行に成功(59秒、260m)しましたが、
「動力なし飛行機」で成功したのはドイツ人のリリエンタール。1893年か94年頃とされています。
日本で最初に動力飛行機で空を飛んだのは、1910(明治43年)12月14日。
日本陸軍の日野熊蔵の乗ったドイツ製単葉機ハンス・グラーデが代々木連兵場の滑走路を駆け出し、ふわりと空を飛びました。
飛行距離25m。第2回目は60m。まさに歴史的な瞬間です。
ところが、なぜか日本では「日本初飛行の日」が12月19日とされています。
そのわけは、この日に陸軍の徳川好敏大尉がフランス製複葉機アンリ・ファルマンで3000mを飛行しているからです。
同じ日、日野も700mの飛行に成功しているのですが、
軍としては「徳川」の血を引く人間に栄誉を与えたかったということでしょう。
さてさて、本公演の主役の一人である杉坂初江(18)が初めて飛行機が飛ぶのを見たのは明治44年(1911年)3月。
大阪市にあった城東練兵場の上空を、アメリカのボールドウィン飛行団のマースが持ち込んだカーチス式複葉機が大空を飛び回りました。
飛行場が整備されていなかった航空の黎明期、
飛行機の離着陸は主に練兵場、競馬場、砂浜、原っぱなどで行われていました。
日本最初の飛行からわずか3か月、関西では最初の飛行ということもあり、
初江でなくても見た人は心を奪われたことでしょう。
以後、同練兵場は飛行のパイオニア達の舞台となったそうです。
当時の人にとって飛行機は無限の可能性を持った、人間の夢の象徴であったといえるかもしれませんね。
今回のお芝居は初江が歴史的飛行を目撃した半年後のお話です。
文責 松本圭右(舞台監督)
|
|