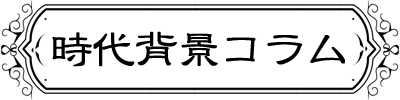
第3回 「女子師範学校について」
■そもそも師範学校とは
1871年に公布された学制に基づき、
東京の湯島聖堂内に官立の師範学校が設立されたことが師範学校のはじまりです。
師範学校は、卒業後教職に就くことを前提として、授業料がかからないのみならず生活も保障されたため、優秀でも貧しい家の子弟への救済策の役割を果たしていたようです。
師範学校→高等師範学校→文理科大学というコースをたどれば、学費無料で
中等学校→高等学校→帝国大学というルートに匹敵する教育が受けられたとか。
このため、経済的な理由で進学を断念せざるをえない優秀な人材を多く吸収したそうです。
今回の作品だと初江もこの制度に助けられた、ということになるのでしょうか?
しかし、師範学校の寮生活において、学校によっては上級生による下級生へのいじめ、しごきが問題になり、全寮制を廃止した学校もあったとのこと。
また、卒業生の中には「師範タイプ」と呼ばれる融通の利かない教師もいて、問題視されていたそうです。なんだか今回の作品内にもちょっぴり思い当たるような人物がいるような…?
そして戦後、GHQがアメリカにならって、教員養成を大学で行うように指導し、師範学校側も大学へ昇格する道がひらけたためにこの指導を積極的に受け入れたため、師範学校は消滅しました。
余談ですが、現在の制度ではあらゆる学部から教員免許を取得できるようになっているために教員の質が低下したと考えられ、一時は師範学校制度を復活させる、という議論もあったようです。
結局「師範タイプ」のように画一的な教員が生まれてしまうということや、教職大学院制度などが導入されたことから、師範学校の復活にはなりませんでしたが。
■女子師範学校
1897年の師範教育令により、初等教員を養成する学校の尋常師範学校が『師範学校』と改められ、1920年代後半までに師範学校の女子部が『女子師範学校』として分離されました。
師範学校には本科第一部と本科第二部が定められ、第一部は高等小学校(小学校高等科)卒業を、第二部は中学校もしくは高等女学校卒業を入学資格としていました。
ちなみに高等小学校は義務教育ではないため授業料が徴収され、1936年の統計では尋常小学校(義務教育)卒業者の66%が入学していたとのこと。
中学校や高等女学校となると進学率はガクッと落ちます。
高等女学校進学率は
1905年まで5%以下、1920年に9%、25年には15%…徐々に上昇してはいるものの低い数値。
作中で順吉の言う『難しい試験』というものは調べてみてもよくわかりませんでしたが、入学資格として定められている高等小学校や中学校・高等女学校への進学率から考えると、師範学校に進学できる人間はかなり限られていた…ということでしょうか。
文責 佐藤佑香(装置)
|
|