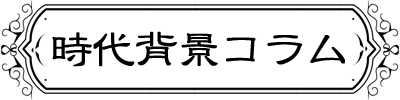
第5回 「明治時代のスポーツ・運動会」
◆近代スポーツの伝来
日本人が欧米のスポーツと接する機会となったのは幕末のペリー来航(1854年)であった。
人々はそこでボクシングの実演を目の当たりにした。
その後、1861年に長崎在留外人によるボーリングサロンの開設、1861年に横浜在留外人により洋式競馬や玉突きの実施を通して舶来のスポーツに触れる機会があった。
対して日本人が欧米由来のスポーツを体験するのは明治時代になってからであった。
留学からの帰国者や牧師、外国人教師により多くの外来スポーツと触れる機会が得られ、
野球・サッカー・陸上競技・テニス・ボートなどが受容された。
これらの多くが移入当初から競技スポーツとして実施されている。
これに伴い、剣道・柔道・相撲といった在来スポーツも明治末期までには洋式化が進められた。
余談であるが『みよひこ』の時代とほぼ一致する大正1年(1912年)に、日本人はオリンピックに初参加している。
◆近代の運動会
わが国最初の運動会は1874年(明治7年)に海軍幹部養成のための海軍操練所で行われた。
当時の名称は「競闘遊戯」で、二人三脚・棒高跳び・肩車競争など17種目が行われた。
その後、明治期の運動会は次の3つの期間に分けられる。
○第1期 明治18年〜20年
この期間の運動会は数校の生徒が合同で、近隣の野原・神社境内・練兵場など広い場所に集まって行われた。
これは各校の生徒が少なかったことや、学校の敷地がそれほど広くなかったことに由来する。
内容については、種目数が3〜11程度で体操種目が多かった。
○第2期 明治21年〜33年
この期の開催形態も第1期同様に連合運動会である。
しかし、異なる点としては種目についててある。
第1期で一桁だった種目数は19〜51と増加している。
内容については、体操科目が激減し、軍事教練的種目が増加している。
なお、51の種目を行ったのは「島根県各学校生大運動会」で、中学校・師範学校生をあわせて2日かけておこなっている。
○第3期 明治34年〜45年
第3期では明治33年の小学校例改正に伴う就学率の増加や、「体操場」を必設するような規定、日清戦争・日露戦争の勝利により軍国主義の色合いによって「運動会は確定事業の1つ」といわれていた。
このような背景のもと、開催形式は連合運動会が主流ではあるが、単独の学校で行う「校庭」運動会が台等してくる。
内容については、体操科目はさらに減少する。
対してこれまでになかったダンスが登場する。
また、この期には遊戯的種目は多彩になり、騎馬競争・片足競争・スプーン競争というものが登場する。
明治期に一貫して頻繁に登場した種目は綱引きで、続いて徒競走が挙げられる。
綱引きは団体種目、徒競走は個人種目の代表とされる種目と考えられる。
青田先生が綱引きに意気込むのもそのためだろうか。
文責 堀田明良(青田作治役)
参考文献
1.寒川恒夫『図説スポーツ史』朝倉書店、1991年、p148-149
2.吉見俊哉 ほか 『運動会と日本近代』青弓社、1999年、p86-106
|
|